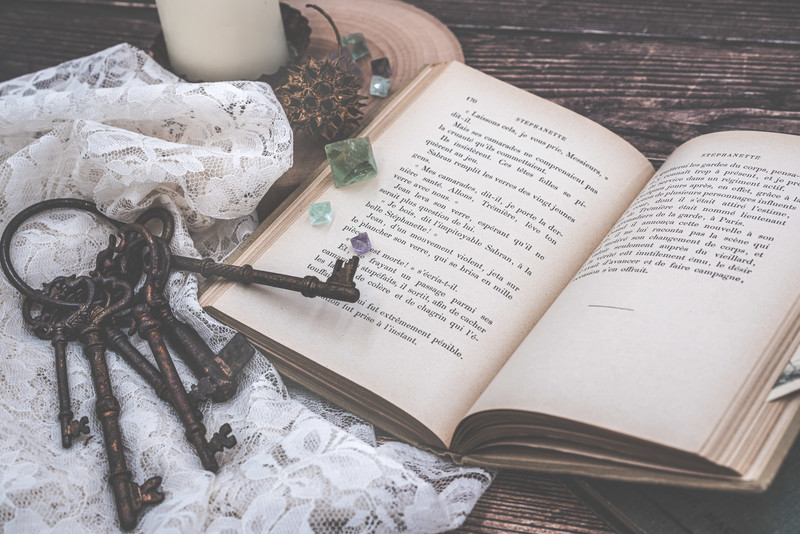行政書士が出版すれば営業が楽になる
行政書士が本を出版することができれば、非常に大きな販促効果があります。
これまで業者扱いされていたのが嘘みたいに、突然先生扱いをされるかもしれません。それほど出版の効果は大きいと思います。私もこれから5年以内には出版することを目標にしております。そのため、いろいろと情報収集をしているところなのですが、いいサービスがあったので紹介しますね。
「企画のたまご屋さん」というサービスがあります。出版したい本の企画書を300社以上の出版社と1,000人以上の編集者に送信してくれるサービスです。著者の有名・無名を問わず、良質な企画であれば、すぐに商業出版が決まったり、複数の出版社から採用通知が来たりするそうです。また、発行部数5万部を超えるベストセラーも続々と誕生しているようです。ただし、よい企画でなければ出版社に送られることなく、ボツになります。
実は私、過去20年間に10回くらい応募しています。テーマはさまざま。行政書士になる前は、バイクのツーリング記録とか、ドライバーで食っていく方法とか、引きこもりから営業マンになった話とか、非正規社員の生き方など、その時に自分が書けそうなテーマで応募をしていました。でも、一切の音沙汰はありませんでした。配信されたけれど、どの編集者の目にも留まらなかったんだなとずっと思っていました。でも、そうではなかったんです。
先日、行政書士の業務関係の本を書きたいと思って、久しぶりに企画のたまご屋さんのホームページを訪れました。そして、ネットから出版企画書を送信。すると、2日後に、企画のたまご屋さんから電話がかかってきました。えっ、出版が決まったの?と喜んだのもつかの間。配信を検討していますとのこと。配信するのではなく、配信を検討とのことらしいです。企画のたまご屋さんとしては、忙しい編集者に配信して、もし彼らの目に留まった時に、企画者に連絡がとれなくては困るから、配信を検討している方には、事前に連絡しているとのこと。在籍確認の電話みたいなものらしいです。
このサービスはNPO法人が運営しており、出版が決まった場合、印税の30%をNPO法人に支払います。つまり、自分の取り分は印税の70%ですね。
出版企画を作成する前にやるべきこと
それは、ずばり、その本がどれだけ売れるかの予測です。ただ予測するわけではありません。出版社の編集者は、出版企画書を精査する前に、その分野の類書がどれだけ売れているかを調査します。どんなに良い本を出しても売れなければ、利益にならないからです。調査の方法は、出版取次会社への調査、ISBNコードからの追跡、アマゾンでの売れ筋調査など、かなりの精度で行うそうです。
そして、ある程度売れると判断した場合に、出版企画書の精査に入ります。内容の精査、著者の精査、価格設定などです。そのテーマでは売れないと判断されれば、苦労して書いた出版企画書は誰にも読まれません。
もちろん、出版社側でできる調査と、著者側でできる調査には違いがあります。ですが、著者だからこそできる調査もあるはずです。表面的には出てこない隠れたニーズに対する調査、書店以外の販売方法、著者買取の最大部数などを補足で書いておくと、もしかすると出版に近づくかもしれません。
出版されるかどうかは企画書で決まる
出版されるかどうかは企画書で決まります。まずは忙しい編集者に読んでもらうこと。だから、2ページ程度で書く。内容は、下記です
① 著者プロフィール
著者の経歴、著者の出版実績、講演実績など
特に本の内容と関連する経歴を重点的に書きます。
② 読者ターゲットの属性と数
どんな読者を想定しているのか。想定読者数については、各種統計資料から信頼性の高い数字を出します。例えば、離婚に関する本を出したいなら、年間離婚件数や離婚を扱う弁護士やカウンセラーの数を調べます。
③ 既存の類書との違い
たいていの分野には既刊書があります。それらと何が違うのか、何を補強しているのかを具体的に書きます。
④ 目次
章立てまでした目次を作っておくと見やすいです。
⑤ サンプルぺージ
最も自信のある記事を2~3本出しておきましょう。サンプルページによって、編集者は著者の文章力を見ますので、法律の専門的な記事ではなく、一般読者向けの分かりやすい記事を作成するとよいです。
⑥ 著者の買取可能部数
本を出版すると、著者は無料で何冊でももらえるわけではありません。たとえ1冊でも著者買取が必要です。ただし定価での購入ではなく、消費税と印税が引かれた額となります。だいたい1500円の本なら、1200円くらいで購入できます。著者の買取部数の目安としては、200部~300部が妥当な線でしょう。これくらいの最低販売部数があれば、出版社も安心ですし、出版への意気込みが伝わります。
出版企画書を通すコツ
① 本の企画に合った出版社に送る
やみくもに送ってもだめ。数打っても当たらない
② ボツになってからが勝負
ご期待に沿えなかった理由を聞く。メールで聞く。
ぎりぎりでボツになった場合は、理由を教えてくれる。
次回に改善する。
③ 書きたい、出版したい、売りたいという気持ちを全面に出す。
出版社としては、売れなければ出版する意味がない。著者のために出しているわけではない。出版社と協力して本を売りたいという気持ちを出した企画書を作る。
④ 出版が決まるまでは、印税の話は一切しない
はじめての出版であれば、そもそも印税には期待しない。出版社にとっては、著者への印税が低いことが出版へのハードルを下げる。つまり低い印税率は、出版可能性を高める。
出版を実現した税理士さんの生の声
先日、実際に出版した税理士さんから話を聞く機会があったので、その要点をまとめたいと思います。
出版するメリットは、事務所のブランド化。出版する前と後では、既存客の態度が違った。また、紹介で訪問した時も、お客様のリスペクト度が半端なかった。
出版のデメリットなのかどうかわからないが、同業者からのやっかみ、ねたみは多少ある。多少ではないかもしれない。アマゾンの書評に、内容のダメ出し、事務所の悪口を書かれることも。内容に関しては、執筆から編集、印刷、製本され、実際に販売されるまで、早くて半年はかかるので、どうしても内容が古くなってしまう。
また、出版界の実情について、リアルな話も聞けました。
無名のビジネス系著者の場合、初版は3000部が多い。ただし、3000部だと、出版社の利益はほとんどない。利益は出ないが、赤字にはならないと判断したら、売上を上げるために出版する。もしかすると重版になり利益が出る可能性もあるから。
出版できた場合、無名著者の場合は、印税5%程度、もしくは買取(50万円前後)。世の中のビジネス書は著者で売れ行きが決まる。なので、なかなか無名著者の企画は通りにくい。最初は、オンデマンド出版も考えてみてはとのこと。商業出版で著者買取200部なら、負担費用はほとんど変わらない。素人が見るとオンデマンドとか商業出版とかわからないことが多いですからね。
出版社との共同出版は絶対にやめたほうがよい
本を出したら人生が変わると言われます。ですが、それは商業出版(出版社側が印刷製本や配本にかかる費用をすべて負担する出版)の話です。自費出版や共同出版、キンドル出版では、人生はそれほど変わりません。
特に、共同出版は絶対にやめたほうがよいです。共同出版とは、本を出したい人を鴨にした自費出版詐欺だと思います。実際は自費出版+出版社の利益をのせた商品だからです。共同出版では、書籍の販売価格より製作費のほうが高いというおかしな現象がおきます。どういうことか、具体例で説明します。
定価1500円(税別)、初版部数1000部で共同出版したとします。仮に完売したとしたら、売上は、150万円。製作費の半分として出版社から請求される金額は、だいたい250万円です。つまり、出版社の言い分としては、本当は500万円の製作費(印刷製本、配本、編集代)がかかっているけれど、著者は半分でいいですよというわけです。
出版社がわざわざ赤字の本を出すわけがありません。実際は、あなたが支払った250万円は製作費の全額+出版社の利益です。
共同出版の本はほとんど売れません。売れなくても、出版社側としては儲かるため、どんどん出版させるのです。そして大量にある売れ残りは、共同出版説明会で、サンプルとして無料で配られるのです。
あと、共同出版のデメリットとして、少し詳しい人が見れば、発行出版社名を見れば共同出版の会社だとわかります。「ああ、共同出版か」と思われると、本を出しても逆効果です。自己満足で出したんだなとか、そんな暇があったら本業頑張ればよいのにとか思われたり、自己満足のために費用と時間をかけて、本業は大丈夫なのかと心配されるのです。